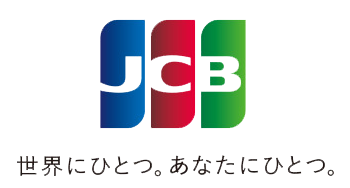〈アース・ウィンド&ファイア、MISIA × 黒田卓也、アンドラ・デイ―〈Blue Note JAZZ FESTIVAL〉が一層気になる各アクトの注目ポイントをズバリ解説! Pt.1 その1>>
text=Hikaru Hanaki

ANDRA DAY
林「僕は毎年ニューオーリンズで行われている〈Essence Festival〉に行っていて、アンドラ・デイは今年そこで観てきたんですよ」
柳樂「どんな感じのライヴでした?」
林「例えるなら、古い映画のワンシーンを観ているようなステージですよ。彼女の作品でも聴けるように、エイミー・ワインハウスやアデルに通じるヴィンテージ・ソウル的なものだったり、クリセット・ミッシェルやジル・スコットのような、ビリー・ホリデイ、ニーナ・シモンからの影響をアップデートさせた感覚のものをやっていました。アンドラ・デイも今回の〈BNJF〉ではサブ・ステージですけど、〈Essence Festival〉ではメイン・ステージに出演していました」
アンドラ・デイの2015年作『Cheers To The Fall』収録曲“Rise Up” パフォーマンス映像
柳樂「それくらいメジャーな人ですよね」
林「そうですね、スティーヴィー・ワンダーの バックアップもあるし。今回アンドラにインタヴューをさせてもらったんですけど、実は僕、彼女のビリー・ホリデイっぽい古めかしいイメージはレーベルやプ ロデューサーの仕込みなのかと思っていたんです。そしたらアンドラはサンディエゴの出身で、南カリフォルニアには大きいロカビリーのシーンがあって、小さい頃から地元のクラシック・カーなどのイヴェントに行っていたんだそうです。そこには1940年代、50年代のピンナップ・ガールみたいな人とか、ビリー・ホリデイやリナ・ホーンを思わせる格好をしている女性がいて。それに影響を受けて、ああいう打ち出し方をしたようなんですよ」
柳樂「ロカビリーのシーンというのが良いですね。エイミーもロネッツやシュレルズみたいな、ヴィンテージなガールズ・グループの影響が見えるじゃないですか」
林「イギリスのエイミーやアデルが、アメリカの古い音楽に影響を受けたサウンドでヒットするのはわかるんですけど、アメリカのアーティストがそういうことをやってメインストリームで受けているのは、実はわりと珍しい」
エイミー・ワインハウスの2007年のライヴ映像
柳樂「ジョス・ストーンも含め、全部イギリス発ですもんね。アメリカをデフォルメしてやっている感じは」
林「こういった 60年代以前のクラシックなものって、実はアメリカの黒人リスナーはそれほど好まないんですよね。だけど最近は、アンドラを支持する人もたくさんいて、彼 女が〈Essence Festival〉のメイン・ステージでやれるくらい人気があることを考えると、アメリカも少し変わってきたのかな、とは思います」
柳樂「ブルックリ ンがお洒落になってきてから、チョーク・アートが凄く流行ったじゃないですか。ああいうのは古いアメリカっぽい感じがありますよね。ちょっと古い家具を置 いたりして。アンドラ・デイはファッションもそうだけど、クラシックのセンスが良い。イギリス的なセンスというか。だから日本で受けそうな気がするんだけ ど、これがアメリカで受けたことに物凄い意義があると思います。アメリカには、とりあえず新しければいい、みたいな雰囲気があるじゃないですか。だからリ ヴァイヴァル的なセンスの良さがあんまりない」
アンドラ・デイの2015年作『Cheers To The Fall』収録曲、ラファエル・サディークがプロデュースした“Gin & Juice (Let Go My Hand)”
林「R&B的な視点でいうと、R・ケリーが何年か前からJBやマーヴィン・ゲイを彷彿とさせる曲を歌いはじめた頃からちょっと変わってきた印象がありますね。アンドラの楽曲をプロデュースしているラファエル・サディークなんかもそうなんだけど」
柳樂「でもアデルやエイミーほどクサくはないんですよね。いまアメリカは古いほうに行くモードなのかもしれない。先日バッドバッドノットグッドにインタヴューをしたんですが、レア・グルーヴの話をしていたんです。マッドリブと かが好きで、彼らがネタにしている音楽を聴いたり、最近買ったネタものっぽいリイシューのレコードが良かったからそれにインスパイアされた、とか。だから レコードが流行っているのと一緒で、古いほうにいく空気があるんじゃないかなと。アンドラはそういった懐古モードのなかのエクストリームな存在であって、 エイミーのようなノーザン・ソウル系とは文脈が違うと思います」
林「そこは単純に (ノーザン・ソウル発祥地の)イギリスとアメリカの違いと言えるかもしれないですね。それにしてもこの人は本当にシンデレラ・ガールって感じですよ。ス ティーヴィーに発掘されたんですけど、それまではサンディエゴの舞台芸術学校に通っていて、好きで歌っていただけ。これといった下積み時代がない、という か見えないんですよね。そういう部分もストリートっぽくっておもしろい。あと、ライヴということでは、コーラスがちゃんと付いていて、非常に品が良いんで すよ。今回コーラスが来るかどうかはわからないですが、バック・バンドは今年の〈Record Store Day〉限定でリリースされた12インチのライヴ盤(『Andra Day Live!』)にも参加していた男性4人。彼らのどこかオールディーズっぽい演奏も、彼女の個性を引き立てていると思います」
2016年の映画「Ben-Hur」のサントラ収録曲、アンドラ・デイ“The Only Way Out”

EARTH, WIND & FIRE
photo by Karston Tannis
林「アース・ウィ ンド&ファイア(以下:EW&F)は2013年の〈SUMMER SONIC〉で来日していたんですよね。僕は行けなかったんですけど、若い子が、(EW&Fは)凄いバンドらしいからとりあえず観てみるかと押し 寄せて、終わったらみんながすごい感動していた、という話がありましたよね。それを聞いた時に、EW&Fもまだまだ行けるなと思いましたし、あり きたりな言い方ですが、本当に世代や国境を越えたバンドだなと。今年、創始者でヴォーカリストのモーリス・ホワイトが 亡くなったんですけど、彼はパーキンソン病を患って90年代の中盤ぐらいから表舞台に姿を見せなくなっていて。それからは名誉メンバー的なポジションで、 2005年作『Illumination』以降はモーリス・ホワイトのいないグループとして活動していました。モーリスのパートは、フィリップ・ベイリーの息子(フィリップ・ベイリーJr)や元14カラット・ソウルのデヴィッド・ウィットワースといった若手に歌わせたりしています。そうやって彼らはいまの若い人たちにも70年代のグルーヴやサウンドを伝えようとしていて、昔のEW&F感はありつつも若々しい。メンバーが替わってもポジティヴな感じなんですよね」
アース・ウィンド&ファイアの2015年のライヴ映像
柳樂「僕も今年の〈サマソニ〉に出ていたラリー・グラハムなど、往年のアーティストのライヴを観たことがあるんですけど、メンバーが全員若くてすっごく上手い。一応若いメンバーもいるからちょっとフィーリングはいまっぽい感じが入るけど、それを出しすぎずにちゃんとかつてのままやっていて」
林「それでも、 EW&Fが来日したり、新作を出したりすると、〈モーリスのいないEW&Fなんて……〉と言う人も結構多いんですよ。でも、モーリスがグ ループの最重要人物であったことを前提として言いますけど、パフォーマンスとしてはフィリップ・ベイリーがいなくなるほうが喪失感は大きいんじゃないかと 思うんですよね。フィリップのファルセットは代えが利かないから。だからモーリスがいないことをことさらに嘆くことはないんじゃないかなとは、いつも思っ ています」
柳樂「〈ルパン三世〉で言えば、山田康雄より栗田貫一のほうがルパン歴が長いらしいですからね。みんな忘れてるけど」
林「それ良い例えかも(笑)」
柳樂「それこそアラン・トゥーサンのバンド・メンバーもめちゃめちゃ上手いわけですよ。アメリカのブラック・ミュージックのヴェテランが連れてくるミュージシャンの尋常じゃない上手さはすごいですよね」
林「ヴェテランは、当人よりもちゃんとパフォーマンスできる人を連れてくることが多い(笑)」
柳樂「代わりに誰かが入ったからガッカリするっていうことはなくて、むしろ若い人を入れることでパワーアップしたりするから。あと今回は、9月に“September”が聴ける!」
林「そうなんですよ。しかも9月17日に開催されますが、“September”は9月21日の思い出を歌っている曲だから、日にち的にもかなり近い(笑)」
柳樂「ちなみにEW&Fは、初期のジャズ雑誌では〈ジャズの未来っぽいやつ〉と紹介されていたんですよね。ジャズがソウル/ファンクに移行した頃に出てきたEW&Fやクール・アンド・ザ・ギャングあたりはそういう扱いを受けていて。モーリス・ホワイトは実際にラムゼイ・ルイスのバンドでドラムを叩いていたりするから、ジャズとは普通に親和性があるというか」
林「特に初期の EW&Fはそうですよね。最初にワーナーからリリースされた2枚(71年作『Earth, Wind & Fire』『The Need Of Love』)なんかを聴くと、本当にジャズですよね。それもかなり前衛的な。ライヴでは“September”は当然やるし、“Let’s Groove”“Boogie Wonderland”“That’s The Way Of The World”あたりはもう定番。でもおもしろいのが“Fantasy”。日本でこの曲をリアルタイムで聴いていた人(“Fantasy”は78年の楽曲) はあれで踊っていた人も多いようですが、実はアメリカでは日本ほど人気の高い曲ではなくて、本国のステージではやらないこともあるんですよ。流石に今回は やると思いますけどね」
71年作『The Need Of Love』収録曲“Energy”
柳樂「へぇー。日本のディスコ・シーンならではの曲だったんだ」
林「そう。アメリ カでEW&Fを2回観たことがあるんですけど、どちらも“Fantasy”はやらなかったですね。しかも“September”もそんなに盛り上 がらない。それは観客のほとんどが黒人だったというのも大きいと思いますが、圧倒的に盛り上がるのは“Devotion”と“Reasons”なんです。 フィリップ・ベイリーのファルセットが冴え渡る曲ですね」
柳樂「“September”はテクニック的な聴かせどころはないですもんね」
林「あと現在のEW&Fには、今回の〈BNJF〉に出演する本家と、元ギタリストのアル・マッケイが率いるグループ=アル・マッケイ・オールスターズの 2つが存在しているんです。アル・マッケイのほうは当時のEW&F感がすごいある。リズムもグルーヴもほんと70年代のまんまで。片や本家は、そ ちらと比べると全盛期のEW&Fっぽくない部分もあるんだけど、時代と共に進化しているのが感じられる。それにやっぱり重厚感がありますよね。 “After The Love Has Gone”のようなバラードになると本家ならではの重みが出るというか。それはヴァーダイン・ホワイトのベースがポイントになっているのかもしれないな。昔からいるコア・メンバーには、精神的支柱を感じさせる見せ場があるんですよね。それと若手も実力派揃いだし、本当に時代と共に進化しているのを体感してほしいですね」
柳樂「最近のアルバムもそうですよね。すごい若いシンガーと一緒にやってる」
林「最新作『Now, Then And Forever』(2013年)はラリー・ダンな ど昔のメンバーも参加していて、往年のEW&F感をストレートに蘇らせているんですよね。たぶん『Illumination』で現行のアーティス トを招いてセルフ・トリビュート的なことをやったので、そこで自分たちを客観的に見つめ直したんじゃないですかね。そういうことも含めて、いま彼らはバン ドとして非常に良い状態にあるんです。そこらへんも改めてしっかり観ておきたいし、今回のフェスではトリを務めますけど、夜空に星や月が浮かんでいたら最 高じゃないですか。そんなシチュエーションで“That’s The Way Of The World”とか“Can’t Hide Love”なんか聴いたら昇天してしまうかもしれません(笑)」
林 剛
70年生まれ。ソウル/R&Bをメインとする音楽ジャーナリスト。音楽雑誌~サイトへの寄稿、CDライナーノーツの執筆、ラジオ番組の選曲などを 行う。音楽書籍の執筆/監修も多数。近著は「新R&B入門~ディアンジェロでつながるソウル・ディスク・ガイド 1995-2015」と「新R&B教室~マイケル・ジャクソンでつながるソウル/ブギー・ディスク・ガイド 1995-2016」(共にSPACE SHOWER BOOKS)。12年間通い続けている〈Essence Festival〉をはじめ、国内外でライヴを観ることをライフワークとしている。
柳樂光隆
79年島根県出雲生まれ。ジャズとその周りにある音楽について書いている音楽評論家。〈Jazz The New Chapter〉シリーズと「MILES : Reimagined 2010年代のマイルス・デイヴィス・ガイド」(共にシンコーミュージック)の監修を務める。音楽雑誌~サイトへの寄稿、CDライナーノーツの執筆も多 数。